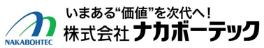EMPLOYEE BENEFITS福利厚生
- TOP
- 福利厚生
当社はワーク・ライフ・バランスの向上のため、
様々な場面で使用できる福利厚生制度を採用しています。
また、従業員への健康促進を図る活動を行い、健康保険組合連合会東京連合会より
「健康優良企業(銀の認定)」として認定されました。
オン・オフのメリハリのある生活を多方面から支援しています。
休日・休暇
-
休日
完全週休2日制、祝日、年末年始(12/30~1/4)、創立記念日(8/27)
特別休暇
結婚休暇(5日)、忌引休暇(3日もしくは7日)、生理休暇(1日/月)、転勤休暇、永年勤続休暇(5年ごとに5日付与)、リフレッシュ休暇※(2日/年)など
年次有給休暇(保留年休)
年次有給休暇最大(20日/年)
保留年休※(上限なし)勤続年数に応じて年次有給休暇を付与します。半日単位の取得も可能です。働く皆さんの働きやすさと健康を大切にし、仕事とプライベートのバランスを取るために、充実した年次有給休暇制度を提供しています。
- 「リフレッシュ休暇」とは、年次有給休暇とは別途年2日の休暇を付与し、オフの時間を作るなど社員への息抜き推進を意図した休暇です。
- 「保留年休」とは、権利が消滅した未消化年次有給休暇を60歳まで積み立てることができる休暇であり、要件を満たした場合に私傷病や育児、介護で必要となった休暇に充当することができます。

補助制度
-
福利厚生サービス
「ベネフィット・ステーション」社員が生活・レジャー等に使用した費用を補助する制度です。
旅行、映画、フィットネス、マッサージ、ゴルフ等様々な分野で使用でき、1人当たり12万円/年まで利用可能です。
また、2023年4月からは奨学金の返済に充てることが可能になりました。財産形成等制度
財産形成等制度には以下のものがあり、いずれも給与の一部の額を財産の貯蓄や形成等に運用することができます。
・社員持株会
毎月一定の口数を拠出することで拠出金に対して5%の奨励金を付与される制度です。
・財産形成貯蓄制度
毎月積み立てた金額について一定額まで利息を非課税とすることができる制度です。
資格取得支援制度
技術士や施工管理技士、技能講習や特別教育等の業務に必要な資格取得にかかる費用や参考書代を補助します。
疾病入院見舞金制度
私病により1日以上入院した場合や先進医療を受け通院した社員に対して、50万円を上限に治療実費を支給します。

-
通勤・住宅補助制度
寮・社宅、住宅手当の支給
一人ひとり個別の住居を会社で契約する借り上げ社宅を整備しており、要件を満たすと割安の個人負担(独身者の場合は月に1万円が家賃として給与から差し引かれます)で入居することができます。
その他、自身で住宅を取得した際に要件を満たすと住宅手当の支給があります。 
-
退職金制度
社内の等級によって支給される「退職一時金」、勤続年数によって一律で支給される「確定給付企業年金」、会社が拠出した掛け金を社員個人が選択した方法で運用した実績が支給される「確定拠出企業型年金」の3つから成り立っており、これらが合算されて支給されます。
・退職一時金
社内の等級によってポイントが決まっており、退職時までの累積ポイントで支給されます。
・確定給付企業年金
勤続年数によってポイントが決まっており、勤続年数に応じて一律の累積ポイントで支給されます。
・確定拠出企業型年金
会社が拠出した掛け金を社員個人が選択した方法で運用した実績が支給されます。

育児・介護支援制度
育児休業制度、育児短時間勤務制度、育児による在宅勤務制度、看護休暇制度
※法定の基準を上回る制度を設けています。
| 制度 | 当社の制度 | 法定制度 |
|---|---|---|
| 育児休業の期間 | 子が3歳に達するまで | 子が1歳に達するまで |
| 子の看護休暇の子の要件 | 子が小学校第6学年の終期まで | 小学校就学の始期に達するまでの子 |
| 子の看護休暇への権利が消滅した未消化年次有給休暇(以下、「保留年休」という。)の充当 | 時間単位で保留年休(有給)を充当 | 定めなし |
| 介護休暇への、保留年休の充当 | 時間単位で保留年休(有給)を充当 | 定めなし |
| 育児のための所定外労働の免除の子の要件 | 子が小学校第6学年の終期まで | 3歳に満たない子 |
| 育児短時間勤務の子の要件 | 子が小学校第6学年の終期まで | 3歳に満たない子 |
| 育児短時間勤務の所定労働時間 | 5時間~6時間30分の範囲内で認める | 6時間 |
| 介護短時間勤務の所定労働時間 | 5時間~6時間30分の範囲内で認める | 6時間 |
| 復職後の勤務 | 育児・介護休業後の社員が円滑な復職ができるよう会社として最大限の配慮を行う | 定めなし |
| 再雇用エントリー制度 | 育児・介護を理由に退職した社員が再勤務する意思がある場合、優先採用に努める | 定めなし |